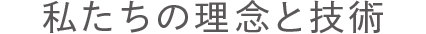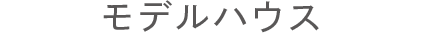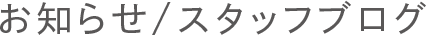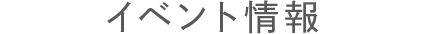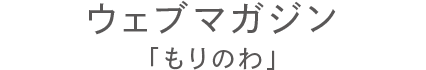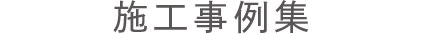事業の起こりと森、地域
私たち坂元植林の家の「共生」を考えるうえで、
まずは事業のルーツからさかのぼらなくてはなりません。
坂元植林の家の出発点。
それは鎌倉時代まで遡ります。大沼毅彦現社長は17代目。
1325年ごろ(鎌倉時代の正中年間)に大沼社長のご先祖様が柴田町坂元に移入し、
現在の場所に家を建てた時がルーツとされています。
以降、大沼家では江戸時代まで、地域で農業を営みながら暮らしていたそうですが、
社長から数えて5代前の大沼半左衛門(はんざえもん)さんの代の頃に日本史を揺るがす大きな出来事が起こります。
明治維新です。
その後、明治4年に行われた廃藩置県により、地域の自然が変化し始めます。
それまで伊達藩によって管理されてきた山林が荒れ始めたそうです。
これをひどく憂いた半左衛門さんは、
地域の森を守るために積極的に植林を行ったそうなのですが、
なぜ彼は森の荒廃を憂い、植林を手掛けたのでしょうか?
林業は100年以上の長い時間をかけて、
人の一生よりも長いサイクルで森を育む仕事です。
木を育て、
そして使うためには「地ごしらえ→植林→下刈り→除伐→枝打ち→間伐→主伐」という大変な手間も必要になります。
林業を商売として考えると、お世辞にも儲かるとは言えません。
環境保全が謳われ、研究が進んでいる現在ならまだしも、当時は今よりも緑が豊かであったはずです。
当時の彼の心情をうかがい知ることはできませんが、
半左エ門さんは
“人が生きていくためには森との共生が不可欠であり、
それを子々孫々、後世に残していかなければならない貴重な資源”だと
見抜いていたのではないでしょうか。

大正時代の屋敷の風景
そんな半左衛門さんの植林活動は息子である源太郎さんに受け継がれます。
植林町長が築いた「坂元の森」の礎
毅彦社長から数えて5代前の大沼半左衛門(はんざえもん)さんの植林活動は、息子である源太郎(げんたろう)さんに受け継がれました。
源太郎さんの代では、林業や農業に留まらず、味噌や醤油醸造など、様々な事業を手掛けていました。特に地域の人々に喜ばれたのは、近隣で採取される良質な岩を切り出す石材業。当時、農業が中心だった地域において、新たな雇用を生み出すこの石材業は人々に大変喜ばれたそうです。
源太郎さんはこのような事業家としての活動だけではなく、町や地域をまとめる活躍もされました。
1900年ごろ、槻木町(つきのきまち)の各地区で所有・管理されていた多くの山林は、乱伐され荒廃してしまっていたそうです。そんな中で、明治41年に槻木町長に就任した源太郎さんは、地区の財産を統一し、植林事業を通して山林の荒廃を防ぐとともに、町の将来の発展を説いたそうです。しかし、議会においては議論が噴出し、各地区の利害の調整も難しく、なかなか理解が得られなかったそうです。
その頃、槻木町では、阿武隈川・白石川の氾濫が頻発し、農地が大きな被害に遭っていました。そこで源太郎さんは、町から復旧にかかる費用を捻出し、復旧工事にあたったそうなのですが、結果、町民の意識が変わり、こぞって各地区の財産が町に納められるようになったそうです。
こうしてバラバラだった各地区が一体となり、各地区の垣根を超えて復興活動のみならず、植林活動が行われるまでになります。その後、植林により整備された山林がもたらす収入が、町の財政に大きく寄与することになります(立役者である源太郎さんは、当時“植林町長”とあだ名されていたそうです。ちなみに彼が取り組んできたこれらの功績をたたえ、槻木西地区の葛岡公園に顕彰碑がありますので、ぜひ一度足を運んでいただきたいと思います。)

顕彰碑
災害と一人の人物をきっかけとして、まとまりを見せ始めた地域。そして植林活動により、その関係性が強化されることになるわけですが、そのような中で1908年(明治41年3月17日)、源太郎さんは、坂元(さかもと)植林(しょくりん)合資会社を設立。以降、サカモトのDNAともいうべき“森と地域に対する想い”は現在へと脈々と受け継がれることになります。