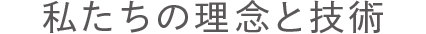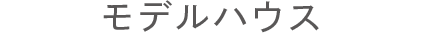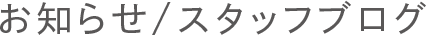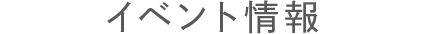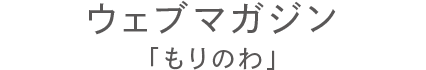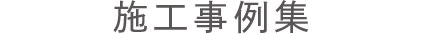第2回 自然の理解と環境建築
自然と共にある設計思想の話|山田貴宏さんインタビュー

ご自身のお住まいでもある、エコロジカルな生活を可能にする「里山長屋」のお話に続いて、長屋での暮らしぶりのこと、そして、山田さんが建築家として長年、志向し探究されている「環境建築」についてお話を伺いました。
第1回の公開からこの第2回の公開まで、時間が空いてしまいましたが、その間に、山田さんが設計を手掛けた弊社の「さとのえ」が、2023年度の「ウッドデザイン賞」で最優秀賞の1つ「環境大臣賞」を、また、日本建築エコハウス大賞のモデルハウス部門で「優秀賞」をいただくことができました。いずれも、自然のめぐみを存分に生かし、現代的な技術も取り入れた山田さんの環境建築が、現代のさまざまな喫緊の問題への対応策として評価いただいているからこそと理解しています。本稿では、里山長屋での暮らしと、そもそも「環境建築とは?」について語っていただいています。(もりのわ編集部)
第1章 里山長屋での暮らし ― 環境的な建築家としての自問自答
–第2回「自然の理解と環境建築」

光、風、水と、里山長屋の暮らし
先にお話したように、里山長屋は、最初は4家族で、自分たちで出資し合って作ったコーポラティブハウスなんですが、入居後しばらくして、1家族は今、ニュージーランドへ行っていて、不在の間、賃貸として入居者を募集しました。数家族がこれまで入居していますが、現在入居されているのがアメリカ人と日本人のご夫妻です。この長屋周辺の集落には100世帯くらいの家族が暮らしていますが、そのうちの5、6世帯はアメリカやブラジル、ルーマニアから来た方がいる世帯。余談ですが、近くの他の集落には、古民家を買って改装して、養蚕をやっているカナダの方も住んでいます。その蚕は、とても綺麗な緑色がかった繭をつくります。自分で桑を育てて、絹糸をとって、織りまで自分でやってしまうんです。養蚕は日本の伝統的な山間地の産業ですよね。それを外国の方が継承していることにも驚きますが、最近では、アメリカからその古民家にワークショップで体験にも来ているそうです。藤野という土地は、自然環境の中で、その自然のめぐみを上手にシェアしながら暮らしを立てていく、そういう価値のわかる人たちが、地元の人、移住者問わず、この土地の文化をつくっているように思います。
里山長屋の建築については、土地ありきでスタートしたので、最初は、その存在をあまり意識してなかったんですけど、でも、暮らし始めてみて改めて気がついた。それが、敷地に隣接してヒノキ林があることなんです。

その林が、夏は冷気だまりになっているので、気温が2度ぐらい違っていて、林の側の窓を開けておくと、その風が入る。だから、暑い季節は、夜寝るとき、北側の1階を開けて、2階も開けておくんです。その一方で、南面は、ぽかぽか日が当たっていて暖かい。だから、意識したのは上下の空気の抜けです。上下の温度差で空気の動きができて、1階に溜まっていた暖かい空気が上へ動き、北から抜けていく。そういう風の流れができるんですよね。

ここでは、水の流れもつくっています。これは(上の写真)「井戸ですか?」とよく聞かれるけど、雨水を汲み上げるポンプです。タンクは、1個5000円ぐらいのものを二つ買ってきて。上のコンクリートは型を組んで作ってもらって。 タンクに溜まる雨水は、生活の中で使って、最後は庭の池に流します。いわゆるカスケード利用註1といって、きれいなほうから順次使っていくというやり方です。
池はちゃんと防水処理しましたけど、穴が開いているみたいで、水が漏れちゃいました。3回ぐらい補修しましたが、さすがに誰も今は手をつけてなくて、池があったときの菖蒲が葉っぱだけ残っています。あの池からオーバーフローした水は、畑のほうへ自然と流れていくようには水路は作ってあります。石を並べただけですけどね。

こういうふうに、雨水の恵みから生活の中で流れを作るときに、流れの速さを少しずつ抑制しながら、使っては下に流してあげる、使っては下に流してあげるという繰り返し。下に流すということは当然、汚染されたものは流せないので、いつもクリーンな状態にしておく必要がある。汚染というのは、土が汚れているとかそういうことじゃなくて、ケミカルなものとかそういうものは入れないというマナーが必要になってくるわけです。
環境と建築
建築も、そういう思想でつくったらいいんじゃないかなと思います。建築も同じメタファで語れるように思えるんです。順次、使っていくということですね。作りました、使います、次の世代に渡していきます、と。建築として使えなくなったら、今度は材料として使う。材料が今度、いよいよ使えなくなったら、薪にして、燃料として回収するようなね。灰はまた畑に戻すみたいな。一事が万事、そういう発想で、建築づくりもできるといいなと思うんですけどね。
建物での蓄熱も、そのエネルギーをどう建築にためるか、熱くなったらそれをどう放出するか、流れの中で建築の中にどう留めるかということだと思います。そういう表現をすると、なんか腑に落ちてくるというか。建築は流れを止めちゃいけないということかなと思うんですけどね。
広島の設計者で、三分一博志さんという方が、風や光は、建築の動く資源だと言っています。その考えと表現は、僕も結構しっくりくるんですよね。
昔からある集落で、そこに山からどのように風が吹いて、集落の中をどう抜けて海に流れていくかみたいなことを調べた例があったと思います。調査した人とかは思い出せないんだけど、集落の中で、風をどう配っていくか、そういうことはとっても大事だと思います。昔のことだから、誰もそれを意図してそういう設計をしてるわけではなくて、自然発生的に風の流れを読みながら、建築を作っていった結果、そうなってるわけですよね。それはとても面白いと思う。ルドルフスキーじゃないけど、『建築家なしの建築』註2というか。
では、環境建築って何かと考えたときに、単にトッピング的に、太陽電池が載っていますとか、エコ設備が搭載されていますということではないじゃない、というのは、大前提だと思います。では、何をもって環境的な建築かと、あらためてここ数年、考えているわけです。
パーマカルチャーとか、そういうことの文脈から言うと、自然界への理解とは何なのかということを、あらためてきちんと考えなければいけないと、ここ1年は、ずっと考えています。そういうタイミングでこの「さとのえ」のプロジェクトで、廣瀬さん(外構担当・環境デザイナー)にお会いできたのは、とてもよかったと思っています。
自然をどう理解するかというと、いろいろなアプローチがありますね。生物学を、あるいは植物学を勉強して理解をする方法があるし、精神的に自然を体感する理解の仕方もあるし。あるいは、自然界の中で人間がある営みをしているということを通して自然を理解することがあるし。いろいろな理解の仕方があると思いますが、やはりそこが腑に落ちていないと、建築家は、環境建築を語れないのではないか、と。20年もやってきて、今、そう思うんだから、今まで自分は何をやってきたのかという気もしますが、そこがね、僕の今のテーマなんです。

「流れ」と「よどみ」
非常に雑駁な理解ではあるのですが、自然って一言で言ってしまうと「流れ」なんだろうなと思います。先ほど、この里山長屋の例でお話したように、水は流れる。風は流れる。熱は流れる。エネルギーは流れる。流れていくなかで、あるストックができる。それが植物として固定化されていたりとか、木として固定化されていたりとか。あとエネルギーが凝縮した形が生物だったり・・・。

そのなかで、では建築って何なんだろうっていったときに、こういういろいろなエネルギーとか水とか風とか流れのなかで、ある「よどみ」ができていて、そのよどみが地上に転写されたのが、建築なのではないだろうか、と・・・。非常にポエティックな言い方なんだけど、そういう理解の仕方をすると、僕自身は、とても腑に落ちるわけです。
そうだとすると、その建築を構成している材料は、その土地のある流れのなかで流れてきたものを使ってつくらざるを得ないというか。それが100年後に壊れたとしても、その流れに乗って、また下流に流れていく。そういう流れを止めないような建築というか。よどむんだけど、よどんだところでエネルギーがたまったら、そのエネルギーを使う。熱がたまったら、その熱を使う。風が通れば家を冷やしてくれる。湿気を排出してくれる。だから、なにかそういう文脈で、環境と建築というものを理解する。それがデザインの原則で。それに従ってデザインしていけば、けっこう無理なく設計ができると考えています。
気候風土の中で成立する環境建築
今は新建材で作られる建築が大半なんですけど、それはもう30年で壊されたら全部ゴミだし、とてもとても循環するような家ではないわけですよね。新建材でなければ家が作れないというのだったらまだしも、木と土でできている家というのは、まさにこういう日本の高温多湿な気候風土には合っているんです。それを新建材に置き換えるということは、本来、そこに無理が生じるのではないでしょうか。いくら機能性が上がったとしても。
この里山長屋も、単に昔ながらの方法論を踏襲するだけかといったら、そうではなくて、断熱性はきちんと考えて取り入れているんです。土壁があって、その外側に実は約100ミリの断熱材を入れています。その断熱材をグラスウールとか新建材で作ってしまったら、環境建築の意味が薄れるので、ウッドファイバーという杉の皮をシュレッダーしたものをもう一回断熱材に固めたものと、あとウールと、2種類を使っています。これを約100ミリの厚みで入れています。ということで、昔ながらの土壁の家ながら、断熱もきちんとして、そういう温熱環境にも配慮しています。
こう話すと「確かに断熱がきちんとされた家だね」で終わってしまいますが、この土壁という熱を蓄える性質に断熱をすることによって、この土が生きてくるんです。今日も外はちょっと暑いんですけど、この中に入ったら少しひんやりしたと思うんですけど、それは土が熱を蓄えている。夏の場合は蓄熱でなくて蓄冷になるわけです。
要は、夜のうちに家を冷やしておくわけ。そうすると、昨日なんかもこの付近は夜の間も18度ぐらいですから、その18度の空気を夜の間に通して、土壁を冷やしておくんですよね。そうすると、次の日も家の中がひんやりしています。これから夏になって、気温が32~33度になっても、家の中は午前中はひんやりとしていて、冷房は要らないですね。
昼を過ぎてくると、外の熱気がだんだん入ってくるので、さすがに暑くなってくるんですけど、何とか扇風機ぐらいでやり過ごすことができる。4時、5時になってくればまた気温が落ちてくるから、エアコンはかろうじて今は使ってない状況です。でもね、ここ2、3年はやっぱり猛暑で、さすがにそれもなかなか厳しくなってきましたけど。註3
蓄熱という伝統工法の家が持ってる性質をより生かすための現代の技術というのは、いい使い方だと思います。単に新しいものはだめ、古いものがいいんだという話ではなくて。だから、そういう匙加減というか、古いものと新しいものをコンビネーションとかハイブリッドとか、そういうものを考えたい。単純な話なんですよ。土壁に断熱材入れるだけだから、特殊技術ではなくて、誰でもできる普遍的で一般化できる技術ということなんです。
その手法はうまくいっています。工学院大学の環境系の先生に計測してもらったら、室内の気温の変化がやはりマイルドなんですね。外気温が大きく変動しても、室内は緩やかに変動してる。夏はそういうふうに少し涼しい家の感じだし、冬は冬で、太陽の高度が低くなって、ここはガラスになっていますが、太陽の光がたっぷりここまで入ってくるんです。そうすると、土に熱が吸収される、床も吸収するということで、室温がやはり蓄熱してるんです。だから、夕方になっても、外気温が0度ぐらいになっても、室温は20度ぐらいまでで止まっているという状況が実現できています。

だから、必要以上に暖房を焚かなくても、昼間に得た太陽の熱が暖房の働きをするし、あんまり高断熱にしなくても、そういう温熱環境に優れた家に、むしろ伝統工法だからできるということですね。
そんなことで、この家は出来ています。それから、木と土が吸湿、つまり、湿気を吸ったり吐いたりしてくれるので、それもとても室内の心地よさに寄与していて、夏は湿気を測ると外よりも内側のほうが数パーセント低いですね。面白いことに。逆に冬は湿気を吐いてくれるから、少し高めです。
今、高断熱・高気密を強く重視する家づくりの考え方もあり、いろんな議論があります。省エネにするためには高断熱にするというのは当然で、僕も建築学科の中でも環境系の出身なので、断熱がいかに大事かというのは、よくよく分かっています。でも、結局、統合的でないのではないかと考えています。
いい家といい環境建築は必ずしも一致しない。いい断熱がいい環境建築か、あるいはいい建築かといったら、そういうわけではないのではないかな。いい家で、環境にも配慮していて、断熱もしっかりしているというのだったらいいのですが、今、「とにかく高断熱になっていればエコハウスだ」という風潮もあって、そこに僕は、「違うのでは?」と言うしかないと思っています。(第2章へ続きます)
———
註1:資源やエネルギーを1回だけの使いきりにするのではなく、利用したことで性質が変わった資源や、利用時に出る廃棄物を別の用途に使い、その後もさらに別の用途に活かす、というように、高レベルの利用から低レベルの利用へと、多段階(カスケード)に活用すること。(goo辞書より転載)
註2:『建築家なしの建築』バーナード・ルドフスキー/著、渡辺武信/訳 鹿島出版会SD選書 1984年
註3:お話を伺った翌年2022年の記録的な猛暑の夏、山田家でもエアコンを設置されたそうです。とはいえ、稼働するのは、ひと夏の間に、ほんの数日だけとのことです。